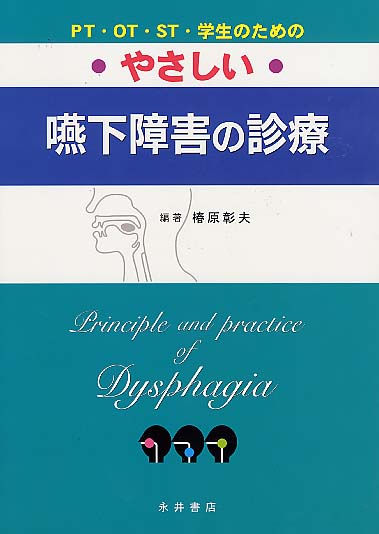■ 序 文 ■
私が初めて嚥下障害の講義を聴いたのは、1981年のことであったと記憶しています。
もちろん、嚥下障害で困っている患者様へのリハビリテーション医療は、その当時の日本にはほとんど知られていませんでした。
嚥下障害患者様にもなんとかして幸せを与えなければならないという講演者の先生の熱い思いは残念ながら伝わらず、私には苦痛な1時間でした。
それは「顎舌骨筋、オトガイ舌骨筋、顎二腹筋、茎突舌骨筋、甲状舌骨筋などが嚥下には重要である」といった解剖学の内容から講義がスタートしたからです。
「大腿四頭筋や上腕二頭筋なら、知っているけど……」と、リハビリテーションを志す医師としての言いわけを考えつつ、あくびしながら講義を拝聴したのを思い出します。
不勉強な私の記憶違いでなければ、医学部の学生時代にも、嚥下機能に関連するこれらの筋肉については、しっかりとは教えられなかったと思います。
その2年後に慶應義塾大学月が瀬リハビリテーションセンターで働くことになった私のところへ、嚥下障害患者様が次々とやって来ることになりました。
「もっと真剣に勉強していればよかったのに……」と後悔しても、時遅しでした。
障害者を救うことがリハビリテーション科医の役割で、私たちが放り出したら、誰もほかに救う人はいないわけです。
このことを考えると、一生懸命に勉強するしか方法がありませんでした。
それで、嚥下造影検査も見よう見まねで始めたわけです。今になって思うことは、顎舌骨筋の名前を知らなくても嚥下障害のリハビリテーションは行えるということです。
舌骨と下顎を結ぶ筋(舌骨上筋群)が嚥下反射時に収縮することさえ知っていれば、筋肉の名称はほとんど知らなくても治療可能なのです。
高齢化社会を迎えた現在では、嚥下障害患者様は後を絶たないほど、たくさん受診されます。
リハビリテーション医療を志すコメディカルの皆さんにとっては、嚥下障害のリハビリテーションを知っていることは必須の事項です。
そこで、昔、私が経験したつらい気持ちをもつことなく、簡単に勉強できる入門書を書こうと決心しました。
徹夜して覚えるような内容は、極力省略しました。
この本は、嚥下障害のことをまったく知らない初心者向けの教科書ですので、推理小説を読むくらいの気楽な気持ちで読んでいただければ幸いです。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、介護福祉士などのコメディカルの皆様とこれから専門職になることを目指している学生の方々、
あるいは嚥下障害に馴染みの少ない医師や医学生の皆様に読んでいただき、多くの嚥下障害患者様に大きな幸せを与えられる社会を築きあげていただきますようお願い申し上げます。